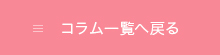医院情報
医院情報
-
- 住所
- 〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
JR名古屋駅コンコース
ファッションワン内
※アクセスの利便性も良いため、名古屋近郊以外にも、岐阜・三重からの患者様にもご来院いただいております。 -
- 電話番号
- 0120-455-758
-
- 診療時間
-
月・火・水・金
9:30~18:30
-
土・祝
9:00~18:00
-
- 休診日
-
木曜・日曜





 0120-455-758
0120-455-758